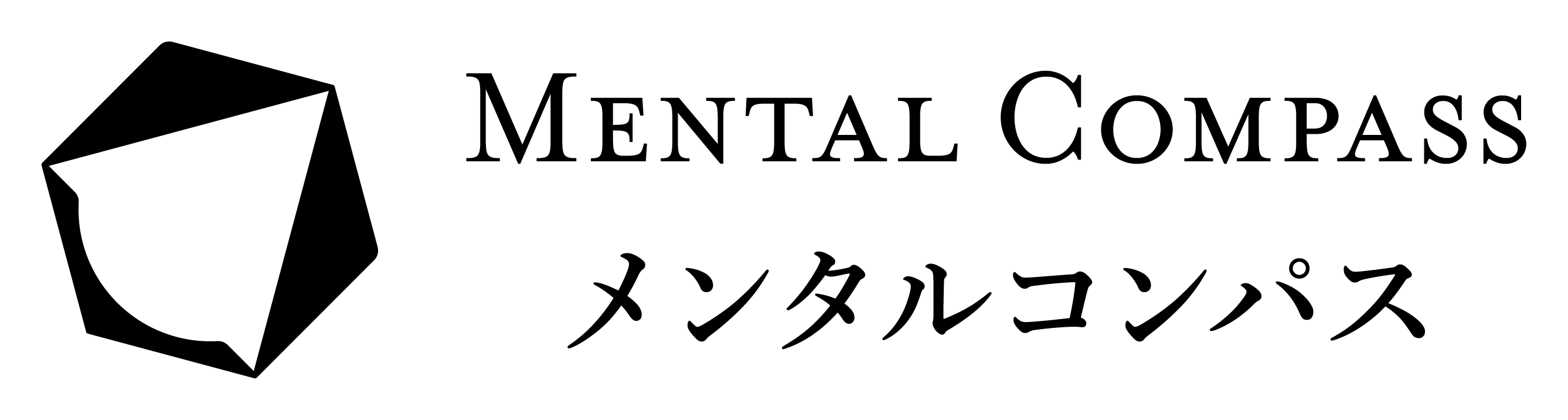大槻経営労務管理事務所
「ソダーツ」を使う前の組織課題
今までは私が指示をしてやってもらう形で受け身だった。職員同士のコミュニケーションの希薄までいかないけど、ヘルプの出しにくさが課題感としてあった。こちら側から何かをお願いしてやってもらう、こうして欲しいという提案は上がるけど、本当はこうしようと思うという実行ベースであがって欲しいと考えていた。
大勢の場で意見を積極的に発信するのが活発になったもらいたいと思っていた。受け身な方が多い印象というのは、長所でもあって、指示を伝えればやってもらえたけど消極的で、調整をしてあげないといけない。勝手にやって失敗してもらいたいという気持ちがあった。
出入りが多かった。サイボウズで予定を入れてやっていた。チームメンバーの共有はできたけど、入れたスケジュールに縛られるのが課題だった。個人が判断できずスケジュールがキツくなって残業が増えてしまっていることを解決したかった。
自分の仕事は責任を持ってやるけど、組織のことは管理職という意識が強い。提案してくれるけど、管理職がやるんだよねという意識が強かった。
「ソダーツ」のファーストインプレッションを教えて下さい
最初はよくわからなかった。概念は教えてもらったけど抽象的。ノーベル賞はわかったけど、どう現場に落とし込むのか?いい方向に行くのか?は、最初な何をやっているのかわからないという気持ち。誘導してくれるがままやっていくうちに、実際に行動に移る部分が徐々に出てきた。
一番最初説明された時はわからなかった。ネガティブなところではなくポジティブな情報を集約するとよくなるというのは今までその方法はとってなかったし、やってみたいなという印象が強烈に残っている。
最初は戸惑った。どういうものかわからなかった。どうしていけばいいのか?と思っていた。チームで関わり合うと、明確に他の人が考えていることがわかるようになった。
AIってそんな具体的に行動出してくれるのかな?と思った。メンバーが5,6人でやっていたけど伝わりにくかった。これで何が改善したか?というのがわかりにくかった。コミュニケーションを進める中で、課題が見つかって改善されていった。
最初わからないことはなかった。行動につながることが良いなと思った。管理職だけだとみんなが行動することはイメージできなかったなと思う。どうなるんだろうと思っていたけど、チームごとになって、この人を助けたいとか無理のない範囲でできるんだろうな、チームで実施した方が効果が高いと思っていた。
「ソダーツ」を実際に使ってみて
参加しているメンバーが葛藤を持つようになった。上から言われたものではなく自分で決めたことを主体的に動く、お互いのタスクも知っているのでこういうところを手伝いましょうという流れができているのがすごく良い。最初はわからなかったけど、それぞれが自然と自分の役割で動けるようになったのが大きなこと。参加しているメンバーがリモートのメンバーもいるけど、機会的に作ったのではなく自然と作られた役割を持って、お互いに手伝う流れができている。自分があれやれと言わずに、自律的に行動できるようになったなと感じています。
ポジティブなことを挙げるので、挙げた結果のネガティブ感がないのがあげやすかった。承認の文化がまだまだ醸成されてないのに気づいた。最初は出てこなくて悩んだり、承認してありがとうっていう文化ができてないという気づきがあった。ポジティブなことを集める。その中でポジティブが出てこないことで、ここが悪いよなというのに気づいた。結果、参加している人が自分たちでやりますという宣言をして動いてくれる。その場で決めたから、こういうことしたいんですというのを話をしてくれたり、自分で考えて実行してくれたと感じたのがやってきて良かった。チームとして変わったと思う。
出ずらいところがわかってくる。時間かかるところがわかってくる。そこにフォーカスをしたくなる自分がいる。良い面を伸ばすのは行動しやすかった、その方が浮き彫りになるのが面白かった。
同じチームのメンバーでやっているので、雑談レベルで終わった後に話をしている。毎回同じようなことを書いていた。チームでやっていることが参考になる。チームの協力として同じ部内でスケジュールを確認して協力を求めたり活発になってきた。
組織のための何か大きなことを掲げて、結局できないことが多かった。最初はソダーツでもそんなこともあったが、やっていくうちにこの1ヶ月の出来事、に紐づけて意味付けして行動することができた。無理なく行動していることが自己肯定感に繋がったのが素晴らしいなと思いながら見ていた。
「ソダーツ」で実際に何が変わったか?
実際に変わったことは、自分たちからメンバー間で助けを求め合えるようになっている。やっていく中で、助けたいと思っていたけど何を助けたらいいかわからなかったという感想があった。その2人がお互いのタスクを認識しましょうとなり、ミーティングするようになって、助け合いが深まってきた。さらに「この日にこういうタスクが発生してこれくらい人手が足りない」と発信して、それに反応して「私が助けます」というサイクルが回っているのが変化だなと思います。
メンバーの実行する目標、行動が定期的に情報確認が多く挙がっていた。その結果、密にコミュニケーションとっているというのが変わってきた。状況は変わってくるので朝こうだと思っても変わってくる。そこのコミュニケーションをとる機会がだんだんと増えている。そういうところからスタートしていくのかなと。反応も早くなっていく。できていることの安心感も出てくる。
一番変わったなと思うのが、各メンバーの状況を把握しようから始まった。始める前はスケジュールが真っ白だった人が、スケジュールを詳細に入れてくれて、お互いが何をしているかを共有した。それが習慣化されていて入ってないと気持ち悪いと感じるようになった。変わったのは見える化、自主的にサイクルを回していくところが変わった。
リーダーがいなくても声掛けあいながらミーティングできているのが頼もしい。リーダーがいなくても自動的に集まって自発的に、真ん中に出るのが好きではない人も管理職的な発言をしているのが頼もしい。管理職は大変。助けてもらう、メンバーを頼って楽になるように関係性が作られていくと良い。
「ソダーツ」でこれから解消していけそうな課題
今回、まだ初めてのことだったのでメンバーの選定も声かけやすい人だけど、機能してきて主体的に役割を実行できている。だから、組織全体で広げていきたい。助け合えるようになったら良いと思っている。
比較的に前に出てくれそうなメンバーを集めて動き出している。その2人でも変化するのでもう少し他のメンバーに使っていけばもっと大きな動きになるのではないか?と思う。階が同じメンバー同士でやって、お互いが認識した後の協力関係が難しい。どんなタイミングが忙しいかという共有をしていきたい。
大元がわかったほうがやりやすい。タスクを決めて自分でやると動きやすい。メンバーの目標のコミュニケーション。やりたいことが事務所全体に関わることは、支持してもあまり進んでいない。逆に収拾つかないので程よいところに落ち着けようかというのは解消したいなと思っている。
興味持っている人もいるので事務所全体チーム全体で実施すればより良い組織、チームになるのではないかと思っています。
上の層のところでやるのは面白い。部署間の連携は課題。課題を感じているけど歩どこまで協力していいかからない、チーム同士の連携が担保できれば良い。
チームメンバーの感想
チーム内でのコミュケーションが増えた。自分たちで判断できる範囲が増えてきた。話しておいた方がいいこともわかるようになってきた。作業のスピードは上がってきた。
目的がふわっとしていたけど、やってみてすごく助かった。業務の分担とかやってみるとむちゃくちゃやりやすくなった。反対意見で飲み込んでいたことを出すことができたこれは心がけていきたい。
参加し始めた頃は半ば、受け身だったけど、自分の側から発信する機会が増えてきた。進捗の透明化、目標の共有などチームワークが意識できたり、成長に役立った。
コミュニケーションを密にとる機会が増えた。言語化、感謝、進捗、伝えないと変わらないし動かない、コミュニケーションとるきっかけになった。批判することもないと思うけど全体に言うのはハードルが高い。免罪符として使ってコミュニケーションとってと言う方向に進んでいる。
ミーティングで確実に自主的に動いて発言するのをみている。ちゃんと発言しながら実行できていることが変わってきた半年だなと思った。実感としてできている。サンクスカードが目的を持って使っている。
1ヶ月でのスパンが短かった。頭の中で中途半端になったなと思った。もう少し長かった方がいいのかなと思った。
できていないこと、忘れてしまうことはあった。メンバーの入れ替わりが激しかった時に情報を共有することをやっていこうという形になった。一貫していたかなと思います。
毎月やることで目標が立てられた。業務フロー、サイボウズでの共有など、ソダーツで変わり仕事がしやすくなった、役に立ったと思う。
き継ぎのタイミングでソダーツに参加した。動詞が多くなった方が良い。質を上げている時にどう言う内容、動詞が大事だと言うところが実感した。
ソダーツに参加してなかったら個人でやる作業が多かったので、全体をあまり意識しないで過ごしてしまったかなと思う。